「いらっしゃいませ」
本日、ドアベルを鳴らしてきょろきょろと店内を見回しながら入ってくる馴染み客の何人目かを
少し苦笑しながらティファはいつものように笑顔で迎える。
「えーと、…クラウドさんは…」
席にはつかず、カウンターまでおずおずとやってくるとやはり同じ事を聞かれてしまう。
店内の何人かの客もちょっと苦笑いをしているようだ。
「安心しな。まだだよ。…ほれ、今のうちにさっさと渡しちまいな」
客の一人が声をかけると、その男はほっと胸を撫で下ろしたように笑顔をみせた。
「良かった、…じゃあ、これ。ティファちゃんに」
後ろ手に持っていた小さな花束を差し出す。
「あ、ありがとう…そんな気を遣わないでください…店に来てくれるだけで充分なんですから」
それに、と少し頬を染めてぼしょぼしょと付け加える。
「あ、あの…そんなに、その…気に、しないでください」
気にするとは先ほどのこの男が心配していたことだ。
『気にするよ』
店内の客は、今全員一致で同じ言葉を心の中で呟いた。
中には「あの男」の身震いするような不思議な色の鋭い眼光を思い出して青くなったものもいる。
そんな思いを知ってか知らずか、店の美しい店主は貰った花を丁寧にほどき、近くにあった花刺しに生けた。
この日は2月14日。バレンタインデー。各地で様々な風習があるようだが、ここエッジでは男性から女性へと贈り物をするのが主のようだ。
「こんなにたくさん貰っちゃって…みんなにもなにかお礼しなくちゃね」
にこやかに微笑むその女性を男共はうっとりと眺める。
そしてまたドアベルが鳴り、不安げに店内を見渡す客が一人。
同じようなやりとりに、はあ、と何人かが嘆息をもらした。
「じゃ、じゃあ、これ、ティファさんに!」
と嬉しそうに綺麗に包装されたプレゼントを男が差し出したその時。恐れていた事態はやってきた。
からん、と音を立てて「その男」が入ってきたのだ。
なごやかムードの店内は一瞬で張り詰める。ただ一人を除いて。
「あ、クラウド、お帰りなさい」
一段と美しい笑顔を見せる店主の華やかさも今の客たちの心には届かない。ましてやたった今プレゼントを差し出した男など、
見るも無残な表情で、ガイアの絶壁もこれほどではないくらいに凍りついている。
『俺の時でなくて良かった』と何人もの人間が心の中で胸を撫で下ろした。
「…?ただいま」
店の異様な空気に首をかしげながらゆっくりとクラウドは住居へとあがる階段へと向かい、ふとティファが手渡されている包みと
なにやら不思議な表情で固まっている男とを見やった。
固まった男といえば、クラウドの背中の大剣がいつにも増して大きく見えていたことだろう。
「い、いや、ほら、これお菓子なんだけどサ!デンゼル君とマリンちゃんにって、うちのかみさんが…」
クラウドはカウンター内の作業台の上に積まれた贈り物の山を見届けると店内の固唾を呑んで見守っている客たちにも
視線を飛ばし(それぞれが順番に目を逸らした)、ああ、と気が付いたように、
「すまないな、みんな」
気を遣わせてるみたいだ、と照れたように頭を掻いて、
「気にしないでくれ」
こともあろうか僅かに口端をあげ、笑ったのだ。
店内にもう一つ、ぴんと張り詰めた空気が漂ったが当人は気付いていないようだ。
彼女の前では当たり前のことなのだろう、ティファの対応は普段どおりである。
「デンゼルとマリン、もう寝てるから静かにお願いね?」
「ああ、わかった」
カウンターの出入り口越しに声をかけるティファに近づいて軽いキスをすると片手を上げてゆっくりと二階へと消えていった。
しばしの沈黙の後、店内に安堵のため息と、ざわつきが広がる。
「アイツ…笑うんだな」
「どうなることかと…」
「いやしかし…」
「うう…ティファちゃん…」
なにやら泣いているものもいる。
その場でへたりこんでいるさきほどプレゼントを差し出した男をひきあげてやると、
ティファはほんのりと桜色に色づいた頬でにこやかに微笑んだ。
「さ、何をお作りしましょうか?一杯奢っちゃうんだから」
「さて…と」
最後の客を送り出したティファは扉を施錠してふう、と息をついた。
軽い食事を済ませ、カウンターでグラスを傾けているクラウドに声をかける。
「もう少し、飲む?」
「いや、もういい」
クラウドはカウンター内の贈り物の山を見つめているようだ。
「ほとんどお菓子みたいよ?デンゼルとマリンが居るから、みんな気を遣ってくれてるみたいね」
当分おやつに困らないわ、と集めてきた残りのグラスを洗い始める。
ふうん、と気の無い返事が返ってきて、はじめてティファはクラウドの機嫌があまり良く無さそうなことに気付く。
「…クラウド?」
クラウドは返事もそこそこにスツールから降りると空になったグラスを持ってカウンターの中に入ってきた。
ん、とグラスを手渡すと、そのまま何も言わずに洗い物をするティファの隣で作業台に寄りかかる。
静かに、何をするわけでもなくただじっと見つめられてティファは少し頬が熱くなるのを感じた。
逸らすことのない、整った顔立ちのその青年のぶしつけな視線は…あまり心臓に良いものではない。
耐えかねて声をかけようとした矢先、クラウドがゆるゆると口を開いた。
「…ティファは」
「え?」
蛇口をきゅ、とひねって視線をあわせると、やっとその射るような目線が逸れた。
「…ティファは、いつもこうやってたくさん貰ってたなって、思い出してたんだ」
「子供の頃の話?」
うん、と頷くクラウドは目線を下げてプレゼントの山の中からひとつ取り出すと所在無げに片手で玩ぶ。
「遊びのひとつみたいなものだったよね。友達同士あげたりお返ししたり」
ティファは濡れた手をタオルで拭くと、クラウドと同じように作業台に寄りかかる。
「…クラウドは一度もくれなかったけど」
ちょっと尖らせた口元に、クラウドが苦笑する。
「あの頃はな」
…知ってるくせに、と小さくほころぶ柔らかな表情に、ティファもまたふふ、と笑みを漏らした。
「そうね」
少し頬を染めてくすくすと笑うティファをしばしみつめたクラウドは持っていた包みを無下に放って山に戻すと
「…今は違うけど」
とポケットから小さな箱を取り出し、ティファに差し出す。
笑いが止まり、差し出された箱をまじまじと見つめるティファの頬がさらにほんのりと朱に染まるさまを見つめながらクラウドは思う。
こんな表情が見られるのは…俺だけの特権だ。
おずおずと箱を受け取り、嬉しそうに開けてもいい?と聞いてくる彼女が可愛くてたまらない、と。
中身は涙型のピアス。
「…綺麗…ありがとう、クラウド…」
とティファは顔をあげ、クラウドの目を見つめて、ふと気付く。
「これ…」
「うん。同じ色」
不思議なきらめきのそれは、クラウドの瞳の色と同じだった。
「俺みたいだろ?」
つ、とクラウドの片手がティファの頬をかすめ、髪をよけると着けてあるピアスに触れた。
不意をつかれた行動にティファの心臓は一瞬にして踊り始める。
もう片方の手も伸びてきて、…どうやらピアスを外そうとしていることにやっと気付く。
「あ、自分で…」
耳元に僅かに触れる指先の感触がくすぐったくてティファは肩を竦め、その手から逃れた。
「俺が着けたい」
クラウドの微かに揺らめく魔晄色の瞳を見て、ティファはまた少し赤くなる。
その瞳は、…自分を、…求めている時のそれに違わなかったからだ。
こうなってくると、ほんの僅かな抵抗も無駄だと経験上分かりきっているティファは観念して後ろを向き、片手で髪を少しかきあげた。
「…じゃあ、お願い」
後ろを向いたのは、ひとえにその妖艶でもある耐え難い視線から逃れるためであったが。
失敗だったと気が付くのはすぐ後のことだ。
突如両脇から伸びてきた腕に心臓が跳ね上がる。
自分が持っているピアスを取るためだとすぐに理解できたが、どうにも心臓に悪い。
見えないぶん、次に何が起こるのか見当がつかないのだ。
背後の気配が一段と静かなことにひとり気が気じゃない自分がなんだか気恥ずかしかった。
クラウドは後ろからティファを抱きしめるように腕をまわすと、彼女が持っている箱を手ごと包み込んで、ピアスをひとつ取り出す。
それを指の中に包み、外れかけていたピアスを親指と人差指で器用に外すと作業台の上に落とし、
持っていた蒼いピアスを小さな孔にゆっくりと差し込んだ。
静かに胸に沸き起こるもの。それは支配欲。
そんな思考にクラウドは
(案外、…俺もバカな男だな)
と苦笑を噛み殺す。
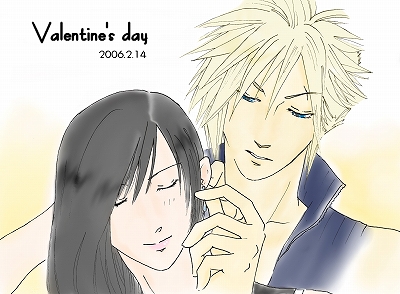
無機質の少し冷たいそれが耳朶を通り抜ける感触。
ティファはその瞬間、微かに身体が反応してしまったことに少しだけうろたえた。
毎日している慣れたはずのその感触が妙に恥ずかしく、他人にされる、というだけでこんなにも違うものかと目を閉じて思う。
いや、クラウドにされているからだ、とあらためて熱くなる耳を隠す術もなくじっとその行為に耐える。
やけに時間をかけてストッパーをはめ込むクラウドが少しだけ憎らしく思えた。
「あ、」
突然耳元に熱い息がかかり、思わず小さな声が零れてしまった。
後ろから耳を舐められて肩が竦む。
「もう!クラウド?」
竦む足をなんとかこらえて腕の中から抜け出すと、悪気のまったく無い表情で図々しく見つめてくるその端正な顔立ちの青年を
思い切り睨み付けるが、こんなに熱くなった頬ではあまり効果は無さそうだと思った。
それはまさしく正解だったようで、余裕の笑みで返されてしまう。
「…似合うよ」
「う…あ、ありがと」
両手で頬をはさまれ、着けたばかりのピアスを指先で玩ぶ彼の唇が降りてくる。
こうされてしまうともうごちゃごちゃとした感情はどこかへ消し飛んでしまうのだ。
「着けるとき…ちょっとやらしいなって思った」
「……ばか」
くくっとその喉元が震えると、耳に口元を近づけてふっと息でピアスを揺らし、
「…俺も、」
耳元でぼそりと何事か囁かれて、ティファの身体がかっと熱くなる。
途端、ふわっと軽々抱き上げられてティファは慌てた。
「あ、…ま、まだお掃除が」
「明日」
「ちょ、帳簿も」
「明日」
「これも、片付けなきゃ」
これ、と言われた贈り物の山をクラウドはじとりと見つめると
「…明日…のゴミに出したいところだけど」
ほっときゃ子供たちが食うだろ、と店の照明を落とし、階段を上がり始めた。
「…クラウドって」
ぷいと視線を合わせないクラウドのシャープな顎の線をまじまじと見つめながら、ティファは言おうとしたことを喉の奥に留めた。
「…なんだ」
「…なんでもないです」
人前でキスするなんて、おかしいと思ってたのよ。
ぷ、と小さく吹き出したティファを一度だけちらりとのぞき見たクラウドはまたすぐに視線を逸らす。
その頬が少しだけ染まって見えるのは錯覚だろうか。
余裕そうなこと言っておいて…と子供染みた横顔をみているとまた笑いがこみ上げてきた。
もちろん、そんなティファの余裕も数分後にはこの男のバイタリティ溢れる所業の数々に掻き消えてしまうことになる。
FIN